 ある高校生のおまじない
ある高校生のおまじない
サージェイドという存在に関わった人のお話。
暖か陽が差し込む教室で、静かな時間が過ぎる。
和やかな雰囲気の授業風景。しかし、オデットの心はざわついていた。
オデットは名門校であるアーテロイド高校で一番の成績を収める優秀な生徒で、容姿も麗しく、全生徒からの憧れの存在。
でもそれは、エレーヌが転校してくるまでだった。
エレーヌは2ケ月ほど前に転入してきた学生で、愛嬌がありとても可愛らしい容姿をしていた。それだけでなく、オデットに負けず劣らずの成績の生徒だった。
生徒からの人気はオデットとエレーヌが二分するようになってしまい、オデットはそれが面白くなかった。エレーヌに負けたくなくて今まで以上に勉強に励むようになり、その反面ピリピリとした雰囲気になってしまっていた。
「ねぇ、オデット。エレーヌって生意気じゃない?」
「え?」
ある日、授業の休み時間に友人のナタリーから言われた言葉は、意外なものだった。
「だって、転校してきたばかりなのに、あんなにチヤホヤされちゃってさ」
ナタリーはじっと横目で教室の端を見遣る。その視線の先はエレーヌの姿があり、その周りには何人かの生徒が笑顔で囲んでいた。
「そ、そうよね…!」
ナタリーの言葉に、オデットの心には今までに無かったエレーヌに対する攻撃的な感情が芽生えた。それはすぐに広がりオデットの心を包み込んだ。
ナタリーはオデットの同意に気を強くし、身を乗り出すようにしてオデットに耳打ちをする。
「帰りに、こっそりエレーヌを追いかけて、どんな家に住んでいるか見てみない? きっとオデットみたいなお嬢様じゃないから、小さな家に住んでるに決まってるわ」
ナタリーはエレーヌの容姿は悪くないが服装が少しみすぼらしいことから、そう思っていた。
「そうね、行ってみましょう」
オデットはナタリーの提案に乗った。ナタリーの予想が当たっていたとしたら、少しでも自分のプライドを保てると思ったからだった。
「あらあら、やっぱり。こんな街外れまで来ちゃって。ねぇ、オデット?」
ナタリーは周囲を見回しながら得意気に笑う。帰宅時間になり、こっそりとエレーヌの後を追っていた2人は、寂れた街外れに来ていた。
オデットは遠くに見えるエレーヌの背中と周囲を交互に見ながら、ナタリーの言う通りだと思った。所々にヒビの入ったコンクリートの道にはゴミが落ちていて、建っている家はどれも小屋のように小さいものばかりで薄汚れている。
「あの家に入ったみたいよ」
ナタリーは声を弾ませて、足を速めた。エレーヌの家は周囲と同じようなとても小さな家で古びていた。
しかし…。
「エレーヌお姉ちゃん、おかえりなさい!」
「ただいま、みんな」
小さな家には、たくさんの幼い子供たちがいて、エレーヌを玄関で出迎えていた。その奥から、顔色の悪い痩せ気味の女性が顔を出す。
「おかえり、エレーヌ。ごめんなさいね、夕飯がまだ途中なの」
「ただいま。母さんは無理しないで寝ていて。洗濯が終わったら、すぐに夕飯を作るから」
エレーヌはそう言ってスクールバッグを玄関に置くと、家の外にある洗濯機の所へ行き手際よく衣服を入れていく。それが終わると狭い庭の草むしりと落ち葉拾いをし、少しした後に家に入って行った。間もなくして、温かな談笑の声が聞こえてくる。
「思った通りね」
ナタリーはオデットに向かって言ったが、オデットはエレーヌが入って行ったドアをじっと見つめたまま呆然としていた。
笑顔の弟妹たち、病弱そうな母、家事を頑張るエレーヌの姿、ぬくもりのある笑い声。裕福であっても、多忙で不在がちな両親の代わりにメイドたちと暮らしている一人っ子のオデットにとって、知らない世界がそこにはあった。
翌日、オデットはナタリーと一緒に登校し、エレーヌの姿を見つけると駆け寄った。
「あ、オデットさん。おはようございます」
エレーヌはいつもと変わらない様子で挨拶をする。
「エレーヌ、あの…。私と、友達になってくれない?」
それは、オデットの心からの想いだった。昨日のエレーヌを見て、同情でも哀れみでもなく、純粋にエレーヌの直向きな姿に憧れていた。
「ほ、本当…? 私、ずっとお友達が欲しかったの! すごく嬉しい…ありがとう!」
エレーヌは目を輝かせてオデットの手を握る。
「もちろんよ。あなたと友達になれるなら、私も嬉しいんだから」
オデットはエレーヌの手を握り返し、微笑んだ。
「な、なによ…。どういうこと?」
手を握り合う2人の様子を見ていたナタリーは、オデットの反応に戸惑い、口を尖らせる。
「ごめんね、ナタリー。私のこと気遣ってくれてるの分かってるから。でも私、分かったの。本当はエレーヌを嫉みたくないって」
「ま、オデットがそう言うなら、あたしは別にいいけど。あんたの気が楽になったってなら、それでいいわ。あんた友達作るの下手なんだから、良かったじゃない」
「うん、ありがとね、ナタリー」
オデットがお礼を言うと、ナタリーはにっこりと笑顔を返した。
そんな2人の隣で、エレーヌは祈るように手を組んで目を閉じる。
「お願い事、聞いてくれたんだ…。ありがとう、サージェイド…」
「え? 何?」
初めて聞く言葉にオデットは首を傾げる。
「実は私ね、友達ができるように“おまじない”をしていたの。それが効いたんだって思って」
と、少し照れ臭そうにエレーヌは笑った。
以来、オデットとエレーヌはお互いに良き友として学問に励んだ。
やがて、2人はアーテロイド高校が誇る最高の才女となり、学問の女神と呼ばれるようになった。そして国民たちから賞賛を浴びる未来となった。
終わる


 うちよそ作品。
うちよそ作品。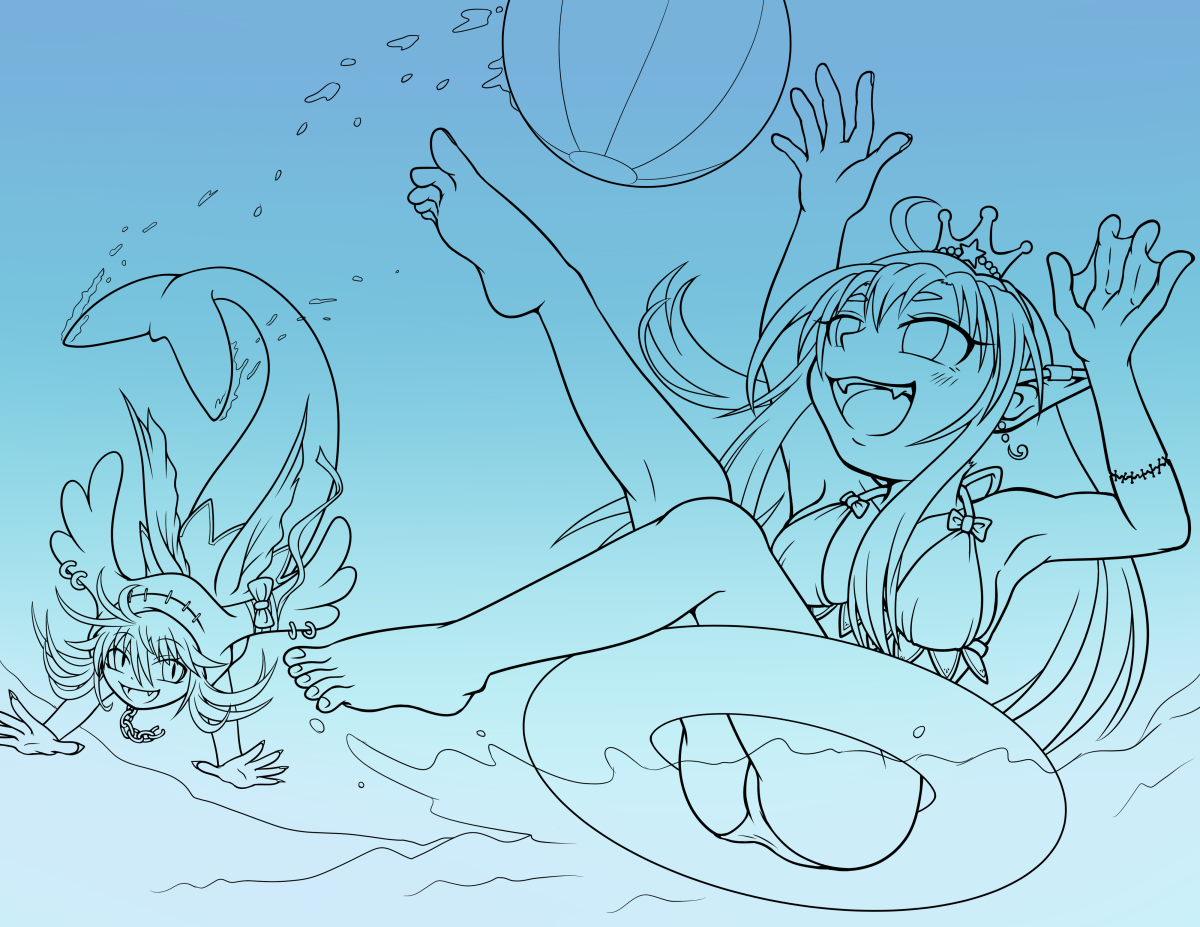 季節外れだけど、うちよそ絵。
季節外れだけど、うちよそ絵。 うちよそ作品。
うちよそ作品。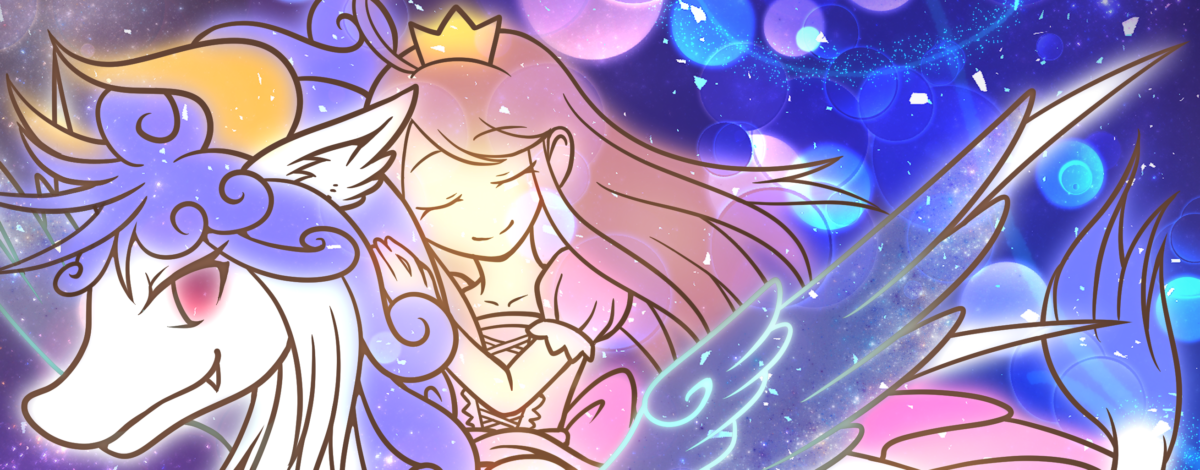 見えぬ世界も、届かぬ想いも。
見えぬ世界も、届かぬ想いも。 宇宙は広いけど、人は人が見て知り考えうる範囲が世界になる。
宇宙は広いけど、人は人が見て知り考えうる範囲が世界になる。